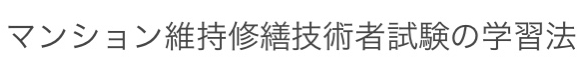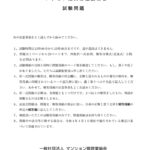択一式試験問題
【問題 1 】 マンションの普及
1.昭和30 年代前半(1950 年代後半)に、民間分譲事業者による 個人向け分譲マンションの 供給が 始まった。
2.昭和30年代(1955 年)に、日本住宅公団(当時)が 大規模な団地の 供給を開始した。
3.昭和50 年代前半(1970 年代後半)では、年間供給戸数が 年々増え、一般的な勤労者世帯が マンションを 取得していた。
4.昭和60 年代(1980 年代後半)では、都心部で 地価が急上昇し、投資用ワンルームマンションの 供給が活発になった。
【問題 2 】 鉄筋コンクリート造建物の壁式構造
1.設計において 構造計画が 容易である。
2.耐震壁と 床版が 箱状の 構造体を 構成している。
3.壁量が多く、旧耐震基準のものでも 一般的に 耐震性が高い。
4.梁や柱の 凹凸がないため、開口部の面積や 位置は 制限される。
【問題 3 】 「マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション標準管理規約(単棟型)コメント」(以下、「マンション標準管理規約」という。)
1.バルコニー等の保存行為のうち、通常の使用に伴って 住戸の窓ガラスが割れたときの入替えは、各住戸の所有者が その責任と負担において これを行うものとする。
2.バルコニー等の管理のうち、計画修繕については、管理組合が その責任と負担において これを行うものとする。
3.バルコニー等の劣化が、計画修繕の周期よりも 短い期間で発生したものであり、かつ、他のバルコニー等と比較して 劣化の程度が顕著である場合は、特段の事情がない限りは、専用使用権を有する者が その責任と負担において 保存行為を 行うものとする。
4.バルコニー等の破損が 第三者による犯罪行為等によることが 明らかな場合の保存行為の実施については、管理組合が その責任と負担において これを行うものとする。
【問題 4 】 マンション標準管理規約
1.不測の事故により 必要となった修繕の経費に充当するために、修繕積立金を 取り崩すことができる。
2.建物の 経常的な補修の経費は、管理費から 充当される。
3.長期修繕計画の作成 又は 変更に関する経費は、管理費又は修繕積立金の取り崩しにより 充当することができる。
4.修繕工事の前提として 実施する建物劣化診断の経費に充当するために、修繕積立金を 取り崩すことができる。
【問題 5 】 建築基準法第12条に規定する建築物の定期調査報告における調査項目等
1.基礎の沈下等の状況は、床等のレベル測定だけでは 施工誤差等もあって 判定は困難であるため、基準点を設け 沈下の進行を 継続観察するなどの 対応が必要となる。
2.タイルの落下により 歩行者等に危害を加えることがないよう、外壁は 必ずしも全面的な テストハンマーによる 打診を行って、タイルの浮きが生じているかを確認するわけではない。
3.補強コンクリートブロック造の 塀の劣化及び損傷の状況は、目視、下げ振り等により確認する。
4.防火扉、防火シャッターその他 これらに類する防火設備の閉鎖又は作動状況は、必ずしも閉鎖又は作動確認を 実施しているわけではない。
【問題 6 】 平成20 年に策定された『「長期修繕計画標準様式」及び「長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント」』(以下、「長期修繕計画作成ガイドライン」という。)
1.長期修繕計画は、将来実施する計画修繕工事の内容、時期、費用等を 確定するために 作成するものではない。
2.長期修繕計画の見直し及び修繕積立金の額の設定については、理事会、専門委員会等で検討を行ったのち、専門家に依頼して長期修繕計画及び修繕積立金の額を見直し、総会で決議する。
3.長期修繕計画の推定修繕工事項目の設定において、長期修繕計画作成ガイドラインの標準様式の工事項目のうち、対象マンションの仕様に該当しない項目については、該当しない旨を明示する。
4.推定修繕工事費は、推定修繕工事の詳細な項目ごとに、算出した数量に 設定した単価を 乗じて算定する。
【問題 7 】 長期修繕計画の推定修繕工事項目、修繕周期及び想定している修繕方法等の設定に関する長期修繕計画作成ガイドラインの標準様式
1.鉄部塗装は、雨掛かり部分と 非雨掛かり部分を分けて、実施する修繕周期及び 想定している修繕方法を設定する。
2.手すりは、取替えについての 修繕周期及び想定している修繕方法を 設定する。
3.屋上防水(露出)は、修繕と撤去・新設に分けて、それぞれの修繕周期及び 想定している修繕方法を 設定する。
4.外壁塗装は、塗替えと除去・塗装に分けて、それぞれの修繕周期及び 想定している修繕方法を設定する。
【問題 8 】 平成23 年に策定された「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」(以下、「修繕積立金ガイドライン」という。)
1.マンションの修繕工事費は、建物の形状や規模、区分所有者の機能向上に対する ニーズによって変動する。
2.マンションは、立地によって 劣化の進行度合いや 必要な修繕の内容が異なり、修繕工事費に 影響を与える場合がある。
3.均等積立方式を採用している新築マンションと、段階増額積立方式を採用している新築マンションは、ほぼ同数とは限らない。
4.修繕積立金ガイドラインでは、長期修繕計画作成ガイドラインにおおむね沿って作成された 住居専用マンション(単棟型)の長期修繕計画を 収集・分析し、修繕積立金の額の目安も示している。
【問題 9 】 調査診断、修繕設計及び工事監理
1.調査診断の目的は、対象建築物の現状の状態を 定性的・定量的に測定・把握し、その劣化の程度を評価・判断し、必要な対策を立案することである。
2.設計者は、設計図書、仕様書、数量内訳書を整え、工事の見積条件を明確にする。
3.施工計画書は、施工者が 自らの施工方法や計画に基づいて 作成する。
4.監理者は、施工中に 工事の進捗を確認し、工事の中間出来高の 審査及び承認を行う。
【問題10】 鉄筋コンクリート
1.鉄筋のかぶり厚さの不足は、腐食やコンクリート剥離などの 問題を引き起こす可能性がある。
2.コンクリートの打設時にできた豆板は、コンクリートの中性化が 進行する原因になる。
3.コンクリートの乾燥収縮は、コンクリートにひび割れが生じる原因になる。
4.建物の不同沈下は、建物の壁面に ひび割れが生じる原因になる。
【問題11】 鉄筋コンクリート造建物の中性化の調査
1.火災で被災したコンクリートが、調査により強度の低下が小さいことがわかっても、中性化の調査は必要。
2.中性化深さの調査のために コンクリートを採取する部位の選定では、骨材が露出している部分は 重要な対象箇所となる。
3.鉄筋に沿ってコンクリートにひび割れが生じている場合は、ひび割れ部周辺の コンクリートを 採取して 中性化の調査を実施した。
4.屋内でも コンクリートの中性化は進行する可能性があるため、中性化の調査は 屋内も対象とする。
【問題12】 鉄筋コンクリート造建物の塩害
1.コンクリート表面層が 円錐状にはく離する スケーリングは、凍害を原因とする 劣化現象である。
2.コンクリート中の塩化物総量は 規制されているため、現在は コンクリートの内在塩化物による 塩害は、ほとんど確認されていない。
3.鉄筋の腐食が 確認されなかった場合、塩化物イオンの浸透自体は、コンクリート強度に 直接影響しない。
4.飛来塩化物が 原因となる塩害は、鉄筋のかぶり厚さが 影響する。
【問題13】 鉄筋コンクリートの劣化現象とその補修方法
1.挙動がある幅1 .0 ㎜程度のひび割れ
2.幅0 .2㎜以上1 .0 ㎜未満のひび割れ
3.幅0 .2㎜未満の微細なひび割れ
4.はがれや欠損が比較的深い欠損
【問題14】 外壁の劣化調査診断
1.目視で行うひび割れの調査では、ひび割れ幅は クラックスケールを用いて 測定することができる。
2.打診法は、打診棒を用いて 仕上げ面を打診し、空洞音を聞き分けて 浮き部を検知する方法である。
3.タイル仕上げの健全度を 調査するために、タイルの接着強度測定を行う。
4.赤外線装置法は、天候、気温、壁面の方位による 影響を受ける。
【問題15】 外壁のタイル張り仕上げ
1.タイルの裏あしの形状には JISの規定がある。
2.地震が原因で、タイル張り壁面に浮きが 生じる場合がある。
3.タイルのモルタル下地に ひび割れが生じると、エフロレッセンスが発生し、タイルの美観が 損なわれる。
4.タイル目地に 目地材を 詰めない深目地仕上げは、意匠上の美観はあるが、タイルが はく落するおそれが 高くなる。
【問題16】 タイル張り仕上げの外壁の補修
1.タイルのひび割れ部は、既存タイルを撤去して、エポキシ樹脂注入工法での補修は 適していない。
2.タイルが浮いている部位は、必ずしもタイルを全て撤去して、下地を補修する必要はない。
3.タイルを張り替えて補修する場合は、タイルの張りしろの厚みに応じて、適切な接着剤を 選択する。
4.躯体から下地モルタルが浮いている場合は、注入口付きアンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法で補修できる。
【問題17】 マンションの内装
1.床の遮音性能の指標である重量床衝撃音遮音等級(LH値)は、L値が大きいほど 遮音性能は 低い。
2.直床仕上げのリフォームでは、下階に配慮し、子供が飛び跳ねたときの床衝撃音対策として、遮音性能の高いフローリング材を 採用した。
3.躯体でない間仕切壁に設置する手すり、照明器具及び設備機器は、壁に下地補強材を あらかじめ入れてから固定しなければならない。
4.天井高が6 mを超え、かつ、面積が200 ㎡を超えるエントランスホールの吊り天井には、構造耐力上安全な構造方法の基準が 定められている。
【問題18】 建築用仕上塗材とその特長
1.樹脂リシンの通称名で呼ばれている 薄付け仕上塗材は、砂壁状に仕上げる塗材として 採用されている。
2.厚付け仕上塗材は、他の塗材と比較して 標準耐用年数が高く、外装用として採用されている。
3.複層仕上塗材は、下塗材、主材及び上塗材の3 層で構成するもので、コンクリート外壁面に 多く採用されている。
4.可とう形改修用仕上塗材は、既存の各種塗装材料に対して 適合性が高い改修専用の仕上塗材として採用されている。
【問題19】 金属用の仕上塗料等
1.マンションの金属面の改修では、速乾性のある 油性調合ペイントが多く採用されている。
2.溶融亜鉛めっき仕上げは、金属面に耐食性を持たせることを 主目的とし採用されている。
3.金属面の塗替えでは、劣化の程度等を考慮し 既存と同じ種類の仕上塗料を 採用しなくてもよい。
4.金属用の仕上塗料は、同じものでも 立地・環境によって適用可否が異なるものがある。
【問題20】 既存塗膜の種別を確認する方法
1.主材の外観調査では、塗膜の仕上げ形状を 確認する。
2.塗料の外観調査では、光沢の有無を 確認する。
3.燃焼試験では、既存塗膜の小片を燃やし、燃焼状態を 確認する。
4.溶剤試験では、既存塗膜が溶剤で 溶解・軟化等の変化が 生じるかどうかを確認する。
【問題21】 鉄筋コンクリート造建物の外壁の塗替え時の下地調整
1.既存塗膜の摩耗が 一部においてわずかに認められる程度であれば、ケレンせずに、部分的に下地を調整する。
2.ひび割れが塗膜全体に 顕著に認められる場合は、ケレンによって 既存塗膜を全面除去して 下地を調整する。
3.変退色・白亜化が 塗膜全体に顕著に進み、ふくれ・はがれがわずかに認められる場合は、高圧水洗で 表面汚染物を除去するとともに、脆弱な 既存塗膜及び素地を除去して 下地を調整する。
4.塗膜ひび割れ部の下地に 2 ~ 3 mm程度の段差が生じている場合は、建築用下地調整材で 段差を調整する。
【問題22】 新築建物に採用する防水工法と施工部位
1.ALC下地の屋根に、FRP系塗膜防水工法・密着仕様は採用できない。
2.下階に住戸があるルーフバルコニーに、アスファルト防水工法・密着保護仕様を採用する。
3.人工池に、アクリルゴム系塗膜防水工法・密着仕様は採用できない。
4.窓のひさしに、トーチ防水工法・密着露出仕様は採用できない。
【問題23】 既存のアスファルト防水工法露出仕様に生じる次の劣化現象
1.平坦部のふくれ
2.平坦部の砂落ち
3.平坦部保護層のせり上り(※保護コンクリート工法での現象のため不可)
【問題24】 シーリング材の劣化現象とその推定原因
→シーリング材を充てんする部位の被着面表面の状態不良
→紫外線・酸化・雨水等によるシーリング材の劣化
→充てん部位に適さないシーリング材の採用
→シーリング材の皮膜の収縮
【問題25】 屋上の防水改修工事における検査等
1.防水施工者の防水施工技能士の資格の有無は、改修工事前に確認する。
2.使用した防水材料の種類・使用量は、品質試験成績書・出荷伝票等により確認する。
3.散水により排水性を確認し、極端な水たまりができる場合の処置は別途協議する。
4.防水層の立上り部及びその端部の雨仕舞の検査は、目視により確認する。
【問題26】 屋上の防水層又はシーリング材の劣化
1.防水層及びシーリング材においては、表面上の劣化と防水機能の低下は、必ずしも一致しない。
2.コンクリートで保護された防水層の劣化調査は、防水層内部を 目視で確認することはできない。
3.防水層の耐用年数は、材料の品質や仕様によるが、おおむね10 ~ 20 年である。
4.シーリング材の耐用年数は、材料の品質や部位によるが、おおむね10 年程度である。
【問題27】 マンションの玄関ドアの改修
1.持出し工法は、既存枠の外側に新規建具を取り付ける工法であるため、既存より開口寸法は若干小さくなる。
2.カバー工法は、乾式工法であるため 短い工期で改修できるが、既存よりも開口寸法は 小さくなる。
3.玄関ドアの枠に 建物変形対応機能をもつ対震枠を採用する場合は、対震ドアガードも設置する。
4.高齢者が ドアの開閉が 容易にできるようにするために、改修時に プッシュプルハンドルを採用する。
【問題28】 板ガラスの種類と特性
1.強化ガラスは強度が高いが、ガラスの表面や小口に傷がついた際は、突然破損する場合がある。
2.線入り板ガラスは、ガラス内部に金属線を通すことで 意匠性をもたせたガラスであり、防火設備用ガラスとして 採用することはできない。
3.複層ガラスには、高い断熱性能をもつもの、日射熱に対し遮熱機能をもつものがある。
4.熱線反射ガラスは、ガラスの片面にコーティングする金属製の薄膜によって ミラー効果を持ち、冷房負荷の軽減が 期待できる。
【問題29】 アルミニウム製手すり
1.手すりの改修工法には、乾式工法と湿式工法があり、接着系あと施工アンカー工法は改修工事に向いている乾式工法である。
2.手すりの改修では、手すりを設置する範囲のコンクリートの強度を確認し、支持方法や支柱間距離を決定する。
3.手すりを壁で支持する方式は、支持金物を設置する手すりの両端で力が分散されるため、躯体への負荷が軽減される。
4.転落防止のための手すりでは、手すり子の内法が110 ㎜を超えるものを設置してはならない。
【問題30】 設備機器・配管の劣化
1.部分的に劣化した鋼管を更新する場合は、異種金属配管接続により生じる電位差が大きくならないよう注意する。
2.給水方式の変更、高効率給湯器への交換、機器・配管の耐震性の強化は、設備等の社会的劣化への対策として実施されている。
3.給水用の鋼管の第1次診断では、主に配管の漏水状態、赤水の発生や水の流量の減少等の状態の調査を行い、腐食状況を診断する。第2次診断では専門家による非破壊診断を実施する。
4.給水用の鋼管の第3次診断では、主に配管の残存寿命の推定と対策の決定を前提とし、既存配管を切断して腐食状況を診断する。
【問題31】 配管設備の劣化の調査
1.超音波厚さ計による調査では、ライニング鋼管の内部より腐食による残存肉厚を計測することができる。
2.X線調査では、対象となる管種を問わず配管・継手の残存肉厚を計測することができる。
3.破壊調査では、亜鉛めっき鋼管の内部腐食状況、腐食減肉部を調査することができる。
4.超音波厚さ計による調査では、残存肉厚を配管外面から調査することができる。
【問32】 マンションの給水方式
1.ポンプ直送方式の長所は、水道本管の断水時でも、受水槽内の残量水を各住戸まで給水できることである。
2.直結増圧方式の長所は、敷地内供給過程での水質汚染の懸念がほとんどないことである。
3.直結直圧方式の長所は、給水設備の維持管理費が抑えられることである。
4.高置水槽方式の短所は、停電時では、受水槽内の残量水は各住戸まで給水できないことである。
【問題33】 給水ポンプ
1.高置水槽方式の揚水ポンプは、通常2台設置され自動相互運転をしているが、一方のポンプが故障すると、他方のポンプが作動して給水する。
2.直送ポンプは、給水量の変化に伴い、ポンプの回転数又は運転台数を変動させて吐出し、圧力を一定に保って給水する。
3.直送ポンプユニットは、ポンプ本体、配管、制御装置等の設備が一体となって設置される。
4.ポンプを床スラブの上に設置する場合は、ポンプ下部に基礎を設け、防振材の設置及び耐震対策をする。
【問題34】 給水管
1.水道用硬質ポリ塩化ビニル管は、直射日光に弱いため、主に屋外の埋設部分で採用されている。
2.水道用架橋ポリエチレン管は、柔軟性があり、住戸部分の給水管に採用されている。
3.水道用ステンレス鋼管は、主に屋内の共用部分の給水管に採用されている。
4.水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管は、管端のさびの発生を防止するために、管端防食継手と共に採用されている。
【問題35】 給水管の劣化調査診断
1.調査診断では、劣化が進行していると想定される箇所の配管を重点的に選定して実施する必要がある。
2.共用部分の配管の調査診断の予算に余裕がある場合は、非破壊調査方法を主体とした上で、部分的に破壊調査を追加して調査する。
3.調査診断では診断の容易性のみを重視せず、調査方法を限定しないことが望ましい。
4.破壊調査は、給水設備を稼働させたままでは診断できない。
【問題36】 給水設備の改修
1.高置水槽方式の改修で直結増圧方式を採用する場合は、既存の高置水槽を引き続き使用して給水することも可能である。
2.受水槽本体を更新する際は、大地震等の災害時に水槽内の貯水を確保するために、緊急遮断弁を設置することを検討する。
3.受水槽の有効容量は、1日の使用水量の半分程度とするが、水道事業体の規定がある場合は、その規定も確認する。
4.劣化による内部の損傷が大くない鋼管及びラニング鋼管の配管内のさび等を除去し、樹脂等によりライニング処理をすることによって既設管を継続して利用する更生工事を採用する。
【問題37】 排水設備
1.屋上の雨水は、ルーフドレン、雨水立て管、雨水横主管を経て排水する。
2.敷地から公共下水道への敷地外排水方式は、現在は、汚水・雑排水と雨水を別の下水管で排水する分流式が原則となっている。
3.排水横管は、排水時の流速が速くなりすぎないよう、適切な流速が確保できる勾配とする。
4.ディスポーザー排水処理システムでは、ディスポーザーで生ごみを破砕して水とともに排出し、公共下水道に放流する。
【問題38】 排水通気設備
1.トラップは、排水管に設置しない。
2.端部を外気に開放している通気管は、排水されていない状態では、排水管内の悪臭ガスを大気に放出する。
3.特殊継手排水システムは、超高層マンションに多く採用されている。
4.特殊継手排水システムは、流速を減じる目的で継手を使用するわけではない。
【問題39】 ガス設備
1.マンションの管理組合とガス事業者のガス配管の資産区分は、地境で分かれており、管理組合は地境以降の敷地内配管を管理する。
2.ガスメーターには検定有効期限があるため、ガス事業者が費用を負担して定期に交換する。
3.浴室の鉄筋コンクリート壁面内に埋設されているガス用亜鉛めっき鋼管の交換目安は埋設後約20年であり、腐食の可能性がある。
4.新規に採用されている埋設ガス配管は、耐食性及び耐震性が高いガス用ポリエチレン管が主流となっている。
【問題40】 マンションの消防用の設備
1.消防法に定める消防用設備等とは、消火設備、警報設備、避難設備、消防用水及び消火活動上必要な施設である。
2.火災の発生や延焼のおそれが少ないものとして所定の基準に適合するマンションは、特例により、「通常用いられる消防用設備等」に代えて「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を設置することができる。
3.消火器の設置個数は、建物の延べ面積又は床面積、消火器の能力で決定する。
4.スプリンクラー設備の設置基準は、消防法の規定のほか、地方公共団体の条例も確認する。
【問題41】 マンションの防災設備の改修
1.既存の屋内1号消火栓は、放水時の吐出能力(放水量)が異なる易操作性1号消火栓に改修することはできる。
2.マンションの竣工後に消防法が改正され、既存の消防用設備等が現行法令に適合しなくなった場合は、遡及適用を受けないものもあるが、比較的容易に改修できるものは新法規に適合させなければならない。
3.屋内消火栓設備を取り替える工事では、消防法の規定に基づき設置された設備について、設置届を提出しなければならない。
4.既存の非常用照明設備に内蔵されているニッケルカドミウム蓄電池(ニカド蓄電池)は、設置から5 年を目安に取り替える。
【問題42】 マンションの換気設備
1.キッチンの換気が有効に行われるためには、レンジフードの排気能力の大きさと共に給気量の確保が重要である。
3.全熱交換器は、空気の給排気の際に、室内外の温度と湿度を同時に熱交換することができる。
4.居室等にホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、新築マンションの各住戸には、原則として機械換気設備の設置が義務づけられている。
【問題43】 空気調和・衛生工学会規格SHASE- S 001 による次の設備図示記号
1.雑排水ます
2.配管固定点
3.一口ガス栓
4.量水器
【問題44】 マンションの共用部分のJISの維持照度
ア.エレベーターホール
→200ルクス
イ.受付
→30ルクス
ウ.階段(非常階段を除く。)
→150ルクス
エ.ピロティ
→50ルクス
【問題45】 分電盤
1.分電盤の配線用遮断器は、経年による感度の変化は生じにくいため、故障をきっかけに更新するだけでなく、定期的な点検や保守を行いながら更新することが必要である。
2.マンションの階段や通路等の照明器具において、昼間の点灯又は夜間の点灯不良などの症状が生じたときは、照明器具やランプに問題が生じていなければ、共用部分の電灯分電盤を調査する。
3.マンションの共用部分の電灯分電盤は、使用経過年数と部品の故障取替えの増加等に応じて、20 年から30 年を目安として盤全体を取り替える。
4.専有部分の分電盤の分岐回路数は、部屋数や居住する人数に応じて余裕のある数とし、将来用の予備として実際の使用回路数よりも3 回路程度を追加して設ける必要がある。
【問題46】 マンションの照明器具
1.照明器具の光源を選定する際は、設置する部屋の使用用途、光源の演色性・効率・寿命を 確認する。
2.LED照明器具は、使用時間が長くなると 照明器具の汚れによって 明るさは低下するが、LEDランプ自身の光束も 徐々に低下する。
3.照明器具の初期照度は、設計照度よりも 2割から3割程度 高くする。
4.天井が コンクリート打ち放し仕上げである場合は、白色系の天井仕上げにした場合よりも 反射率が低くなることを考慮して、照明器具を選定する。
【問題47】建物の区分所有等に関する法律
1.建物の設置又は保存に瑕疵があることにより 他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。
2.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)が 専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を 得なければならない。
3.共用部分の管理に関する事項(共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)及び保存行為を除く。)が 専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
4.建物の価格の2 分の1 に相当する部分が滅失した場合、集会において滅失した共用部分を復旧する旨の決議は、区分所有者及び議決権の過半数の決議によらなければならない。
【問題48】消防法によれば、統括防火管理者を定めることが義務付けられていないもの
1.収容人員が100 人である地上高さ40 mの分譲マンションは、防火管理者の指定が必要。
→高層建築物(高さ31ⅿ以上)のため
2.1 階が飲食店、2 階以上が分譲マンションで、収容人員が50人である地上3 階建の複合用途防火対象物は、防火管理者の指定が必要。
→飲食店が入っている建物で地階を除く3階以上、収容人数30人以上のため
3.1 階及び2 階が物品販売業を営む店舗、3 階以上が分譲マンションで、収容人員が40人である地上5 階建の複合用途防火対象物は、防火管理者の指定が必要。
→物品販売店が入っている建物で、地階を除く階数3階以上、収容人数30人以上のため
4.1 階から3 階が事務所、4 階以上が分譲マンションで、収容人員が30 人である地上6 階建の複合用途防火対象物は、防火管理者の指定が不要。
→収容人数が50人を超えていないため
【問題49】建設業法
1.建設業の許可を受けていないAは、500万円未満の工事しか請け負うことができない。そのため、軽微な建設工事であっても、塗装工事を600 万円で請け負うことはできない。
2.一般建設業は、1件の工事において建築一式工事の場合は、下請契約の額の合計が6,000万円以上、建築一式工事以外は下請契約の額の合計が、4,000万円以上の下請契約はできない。
そのため、Bは、一般建設業の許可を受けた防水工事であれば、5,000 万円で請け負い、当該契約金額の15 %(1,750万円)を元請負人としての共通費(一般管理費等、現場管理費及び共通仮設費)とし、残りの85 %(4,250万円)に相当する額を下請負人との契約金額に充てることができる。
3.都道府県知事の許可を受けたCは、原則として許可を受けた都道府県のみ、建設工事を請け負うことができる。なお、建設工事の請負契約の締結を行う営業所を設置することは都道府県知事の許可を受けていなくてもできる。
4.特定建設業者Dが注文者となる 下請契約における下請代金の支払期日は、原則として、Dが下請負人から工事の目的物の引渡しの申出を受けた日から 起算して 50 日を経過する日以前で、かつ、できる限り短い期間内とする。
【問題50】建築基準法
1.防火地域内においては、高さ2mの門又は塀は、耐火建築物からは 除外される。
2.防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を 隣地境界線に接して 設けることができる。
3.防火地域内にある建築物の屋上に設ける広告塔は、その主要な部分を 不燃材料で造り、又は 覆わなければならない。
4.建築物が 防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、原則として その全部について 防火地域内の建築物に関する規定を 適用する。
【まとめテスト】
記述式試験問題
【問題 1 】 鉄筋コンクリート造建物に生じる劣化現象
コンクリートに外力が作用すると、(引張力)を受ける側に(ひび割れ)が生じやすい。また、コンクリートは(鉄筋)に拘束されているため、(乾燥収縮)すると(ひび割れ)が生じることがある。
コンクリート中の(鉄筋)は、強アルカリ性の環境下では(不動態皮膜)に覆われているため、(腐食(発錆))しない。しかし、(二酸化炭素)の作用を受けて、コンクリートが中性になると、(不動態皮膜)が破壊されて(鉄筋)が(腐食(発錆))し、コンクリートに(ひび割れ)が生じる可能性が高くなる。
【問題 2 】 マンションの外壁の改修に採用されている仕上塗材
(主材)と(上塗材)で構成される可とう形改修用仕上塗材は、(0.5 ~ 1.0mm)程度の塗厚で仕上げる塗材で通称(微弾性フィラー)と呼ばれており、既存の複層仕上塗材に生じた(微細ひび割れ)の充てん補強や、劣化によって硬化した防水形複層塗材(壁面防水材)との(付着性)を保持する仕上塗材として用いられている。
【問題 3 】 既存防水の改修
既存防水を改修する場合は、まず既存防水の状況を確認し、(工法・仕様)は(居住者)に配慮して(煙・悪臭)、騒音又は振動が生じにくいものを選定する。
既存防水がアスファルト防水工法露出仕様で(断熱材)がある場合は、既存の(断熱材)と(防水層)を撤去するか否かを検討し、撤去しない場合は、漏水の原因になりやすい(防水層)の(端部)等のはく離状況や劣化状況を調査し、適切な改修を行う。
【質問4】消火設備について
マンションのスプリンクラー設備は、消防法の規定により(地上11階)以上の階に設置され、火災の感知から消火までを自動で行う消火設備である。マンションに設置するスプリンクラーヘッドの種類は(閉鎖)型であり、そのうち寒冷地のマンションでは(乾式)が用いられる。
(駐車場)に設置できる消火設備には、(泡消火設備)と(粉末消火設備)がある。(泡消火設備)は、燃焼物を窒息・冷却作用で消火し、(粉末消火設備)は、燃焼物を薬剤の負触媒効果で消火する設備である。
【まとめテスト】